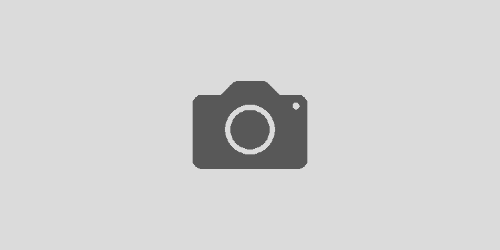工業英検 その2
今回は結果の続きと、勉強に用いる教材等についてまとめたいと思います。
筆者の得点率
合格証書とともに、得点率の票が入っていました。
得点が80%以上か30%未満の場合のみ何らかの記号が書かれるようです。
筆者は設問5(要約&英訳)が80%以上、それ以外の設問は30%以上80%未満の得点率であったということです。
他の設問も結構できたと思っていたんですが、やっぱり高得点っていうのも取りにくいんですね。
ちなみに今回の合格率は40%(受験者169名中、合格者67名)だそうです。
私が受けた東京会場は複数の部屋に分かれて結構な人がいたので、受験者のほとんどは東京会場なのではないでしょうか。
参考書
マイナー試験であるが故に、参考書がほとんどありません。
協会が出している問題集は現在絶版になっており、本屋では手に入りません。
amazonでは高値で売られていますが、内容はどうなんでしょうね?
対策用の参考書としては、コンビニのマルチプリントでお金を払って印刷するもののみが利用可能です・・・・が、高い。
Part毎に別売りで、全て揃えると1,850円。製本されているものならともかく、ただの両面コピーに2,000円弱って・・・具合悪い。
購入方法はこちらを参考にしてください。
筆者は一応買いましたが、特にPart1, 2はほぼ使いませんでした。
「工業英語・テクニカルライティングの本質的なところから勉強したい」という方にとっては参考になるかと思いますが、とりあえず資格だけ取れれば良い、という方には本書を使って勉強するのは非効率です。
Part 3は問題集になっているので、過去問をやり終えて苦手な設問の対策をしたり、不慣れな分野の問題に慣れるというやり方が良いかと思います。
実際の出題形式と異なる問題も相当数含まれていますので、必ずしも全問解く必要はないです。
過去問
過去問もコンビニのマルチプリント機から購入することができます。
筆者は売っているものは全て買いました。
筆者が受けた回(2017年7月)より試験の形式が変更になり、選択問題がなくなって全て必答問題となりました。
そのため、旧形式では自分の得意なトピックスを選べたものの、新形式では受験回によって当たり外れが大きいかなと予想していました(本番では箸にも棒にもかからないような意味不明の分野の問題が出ず良かったです)。
過去問を解いていくと分かるかと思いますが、頻出の分野があります。
・化学(原子の構造、化学反応の説明など)
・機械の説明(飛行機、風力発電機など)
・定理・原理などの発見に関する歴史
・宇宙・地球科学
・新技術
表現の仕方などは、過去問で自己添削して身につけましょう。
なお、筆者はバイオ系のバックグラウンドなので、そういうトピックスが出てくると嬉しいと思っていたのですが、出題頻度は低く、実際の本番でも出ませんでした。
持ち込む辞書
受験を考えている方はご存知だと思いますが、辞書は2冊(電子辞書は×)まで持ち込めます。
筆者はイマドキの若者なので(?)、高校時代は電子辞書を使っていました。
紙の辞書を持っていなかったので、実家から中学時代に使っていたフェイバリット英和・和英辞典を送ってもらい、持ち込もうと考えていました。
が、辞書を使いながら過去問を解いてみたら、単語が全然載っていないことに気がつきました・・・
というわけで、試験用に新たに辞書を買いました。
ネットで多くの方からオススメされていた
『ビジネス技術実用英和大辞典』
『ビジネス技術実用和英大辞典』
を購入しました。
合計1万円の出費ですが、持ち込んだ辞書で合否が左右されるのは納得がいかなかったので、思い切って購入。
中身がちょっと変わっているので(英和も和英も一対一対応で単語の訳が書かれているのではなく、例文の対訳が出てきます)、辞書の性格に慣れるというのも大切な勉強法なのだと感じました。
周りを観察した感じでは、ネットで評判の上記2つの辞書の方よりも普通の辞書の方の方が多かったです(プログレッシブなど)。
とはいえ、ビジネス技術実用英和・和英大辞典はせっかく買ったので、いずれ受けるつもりの1級合格目指して使いこなしていこうと思います。
次回からは設問毎の具体的な対策法についてまとめます。